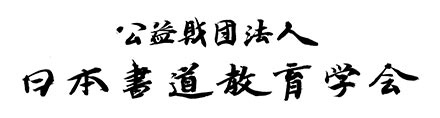優秀作品紹介
不二誌一般版 1月号
漢字条幅
| 支部 | 作者名 | 支部 | 作者名 | 支部 | 作者名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | いち | 榊原 由紀子 |  | 書学 | 藤森 泰明 |  | 書学 | 指田 敦子 |
 | 新書 | 佐藤 光子 |  | 書学 | 川瀬 英之 |  | 水茎 | 川上 直子 |
 | 水茎 | 河合 美由紀 |  | 書学 | 尾﨑 美和子 |  | 宗白 | 飯沼 示衣 |
 | 水茎 | 蔀 久美 |  | 山口 | 大嶋 真弓 |  | 玉桂 | 中村 桂雲 |
 | 川口 | 加藤 北潮 |  | 書学 | 髙瀬 尚子 |  | 新潟 | 坂井 光華 |
 | 水藍 | 新井 俊悟 |  | 書学 | 堀込 真紀子 |  | 文教 | 向山 真由美 |
 | 書学 | 山本 恵市 |  | 梧星 | 髙橋 圭子 |  | 結 | 吉田 香花 |
かな条幅
| 支部 | 作者名 | 支部 | 作者名 | 支部 | 作者名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 東林 | 藤巻 桂泉 |  | 祥瑞 | 河野 愛子 |  | 建中 | 渡邉 翠月 |
 | 月倫 | 清水 君子 |  | 水茎 | 松井 みゆき |  | 芳野 | 山川 智恵子 |
 | 秋月 | 須佐 光宏 |  | 新書 | 新井 順子 |  | 水茎 | 早坂 恵子 |
 | 書学 | 尾﨑 美和子 |  | 書学 | 加藤 晴美 |  | 祥瑞 | 萩原 奈々 |
 | やま | 内山 邦子 |  | 洗心 | 村松 永好 |  | 土呂 | 石原 京子 |
 | 書学 | 田中 しず夏 |  | 北沢 | 小林 純子 |  | 書学 | 大西 司 |
 | 山室 | 押田 チヨ子 |  | 書学 | 藤林 千春 |  | 書学 | 葛西 志保 |
新和様条幅
| 支部 | 作者名 | 支部 | 作者名 | 支部 | 作者名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 神奈 | 坂下 蓉水 |  | 仙水 | 天艸 久美子 |  | プラ | 高橋 久美子 |
 | 芳野 | 山川 智恵子 |  | 神戸 | 摂津 侑子 |  | 水茎 | 半田 喜子 |
 | 万里 | 神之田 澄水 |  | 三重 | 青山 麗泉 |  | 浜 | 立石 可奈子 |
 | 新書 | 坂井 珠江 |  | 書学 | 藤井 顕子 |  | 水茎 | 河合 美由紀 |
 | 愛山 | 加藤 遊水 |  | 華水 | 岩永 房水 |  | 泉汀 | 本山 由美 |
 | 幸丘 | 來栖 智子 |  | 書学 | 大野 真理子 |  | 白雪 | 荒井 和馬 |
 | 紅彣 | 髙 ななみ |  | 書学 | 阿部 文江 |  | 書学 | 増田 玲子 |
実用書
| 支部 | 作者名 | 支部 | 作者名 | 支部 | 作者名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 岩手 | 渡辺 泰安 |  | 愛山 | 加藤 遊水 |  | 琇墨 | 久次 美琇 |
 | 書学 | 梅澤 好子 |  | 西宮 | 雪岡 美佳 |  | 翠風 | 米田 淳風 |
 | 阪二 | 藤井 慶子 |  | 和 | $2014橋 和泉 |  | そら | 池田 昊可 |
 | うみ | 中村 美由紀 |  | 洗心 | 久保 治舟 |  | 鷹番 | 矢川 尚子 |
細字
| 支部 | 作者名 | 支部 | 作者名 | 支部 | 作者名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 伊賀 | 石田 春代 |  | 秀仙 | 鏑木 恵美 |  | 書学 | 北江 恵子 |
 | 書学 | 山本 兎輪 |  | 千翠 | 小宮 富久子 |  | 書学 | 尾﨑 美和子 |
 | 書学 | 細川 美帆 |  | 川口 | 小沢 貴代 |  | 書学 | 遠藤 志帆 |
篆刻
| 支部 | 作者名 | 選評 | |
|---|---|---|---|
 |
藤沢 | 斎藤 修二 | 「月」字を扁平にして、三字二字に布字した満白印。刀がよく切れており、線質も力強く迫力のある秀作。 |
 |
三条 | 福王 鶏石 | 刀法が鋭く、力強く刻しているので線種が多様となり、見応えのある作となった。「透」「窗」の残朱を整理してスッキリさせたい。 |
 |
書学 | 山本 兎輪 | 内輪郭を施し、五字を二、一、二、に布字。線質が良く、太い細いの変化があるので現代的で魅力的な作品である。「明」字は、対角の「斜」字と同等の大きさにすると更によかった。 |
 |
書学 | 渡部 重男 | 二世中村蘭臺の特徴を良く捉えた秀作。模刻は精密さが命。「故」字の偏と旁の接点、上下の枠の長さ、左右の枠の形等原印と再度比較されたい。 |
一字書
| 支部 | 作者名 | 選評 | |
|---|---|---|---|
 |
九書 | 長谷川裕美 | 一字書書法の妙此處にありといった草書の筆捌きを見せている。火偏との一体化を試み「米」で支えて字が立ち構図も見事。竹印の位置もよかった。 |
 |
書学 | 木村 香織 | 爽やかに隷意も以て課題の「燦」を書している。火偏は潤筆で沈着、旁は渇筆を交えて明るく軽妙。落款印も朱色が際立ち字が立ち生気にみつ。 |
 |
三木 | 宮田 雲鶴 | 一見墨象作品にも見えるが、一字書で磨き上げた空間処理が素晴らしく用紙と筆墨共にその特徴を引き出して含蓄に富む。傑作の一つとして残したい。 |
 |
こず | 村岡 初江 | 金文を素材に行書の筆遣いを見せて洒脱な作品に仕上げて味わい深い作品。一字書に取り組んで書することの楽しみを知られたようで新境地を拓いた。 |
 |
こて | 伊藤 紫香 | 墨色もよく出て美しい。紙墨の選択もよい。素人には「な」だと判りにくいが、一画目から二画目へと続く虚線の扱いで奇逸の領域に踏み込んでいる佳作。 |
 |
きし | 中 守楽 | 「(一画目〜三画目)」と「(四画目)」の二筆でマトメての造型。書線の動きも滑らかで爽やか。無理なく書けば、平がな一字を書いても作品となる。 |
 |
文化 | 酒井さだ子 | 文化 酒井さだ子「(一画目〜三画目)」と「(四画目)」の続き具合が窮屈でズレていて一見奇妙な作。しかし、何処か抵抗感があって深い。筆遣いに、年季の入り方の違いを見せている。最初の二筆は古文の草にも見えて面白い。 |
 |
兵庫 | 絹川 佳苑 | 長鋒羊毫筆を使っての一気呵成の作。魅力に富みしっかりしていて、新和様条幅の平がなの文字づくりとしても役立つに違いない。 |